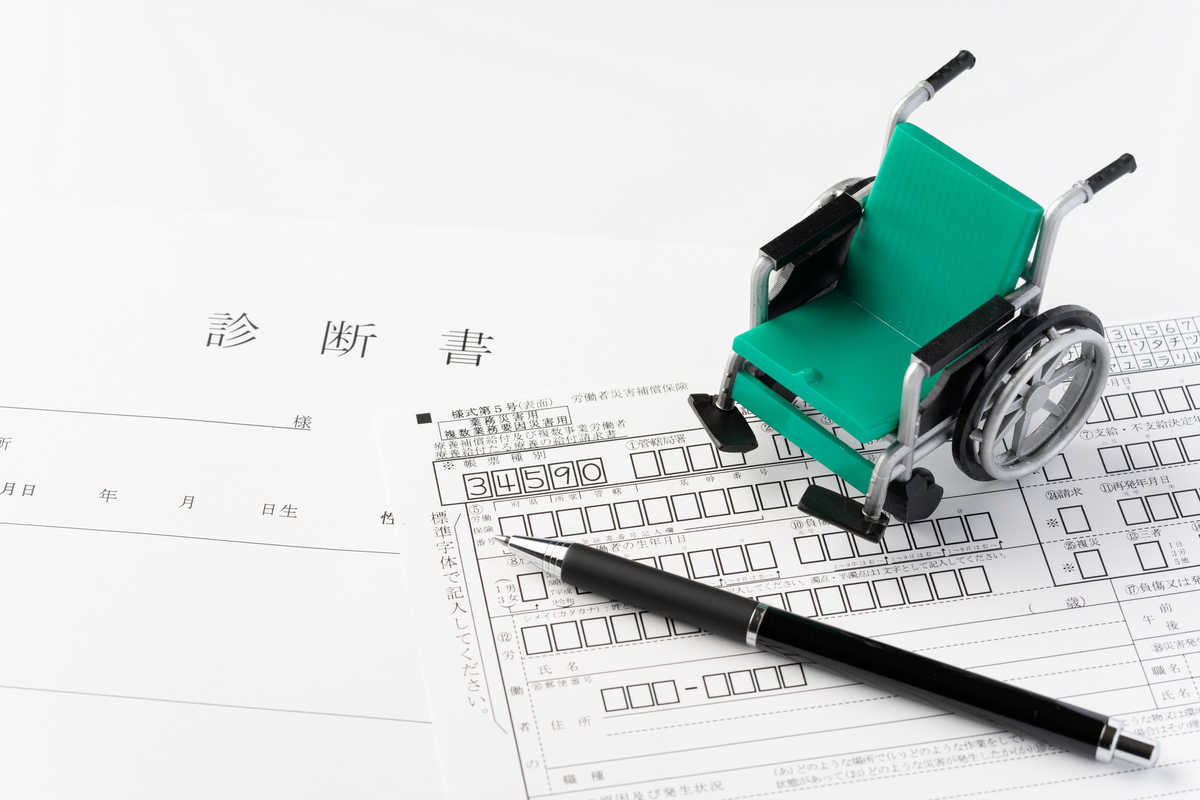
社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
社会保障審議会・介護給付費分科会が15日に開催され、厚生労働省が介護現場における安全性の確保やリスクマネジメントについて課題や論点を示し、サービスの提供に伴い発生した事故情報を収集し、分析・活用をより進めていくための方策について議論を促した。委員からは、再発防止に生かすために全国の事故情報を集約する仕組みを求める声が上がった。また、事業所が市区町村に報告する事故の対象について、軽微な内容も含まれ事務負担が大きいことから、医師が重大事故と判断したものに変更すべきだとの要望も出た。
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)については、運営基準で▽事故発生防止のための指針の整備▽事故が発生した場合の報告と改善策を従業者に周知徹底する体制の整備▽事故発生防止のための委員会と研修の定期的な実施-などを定めている。
2021年度の介護報酬改定では、これらの措置が講じられていない場合の基本報酬の減算(安全管理体制未実施減算)を新たに設けるとともに、外部の研修を受けた担当者を配置して安全対策を実施する体制が整備されている場合の加算(安全対策加算)も新設した。併せて、市区町村によって事故報告の基準がさまざまであることなどから、標準的な事故報告様式が定められた。
現在、介護施設で死亡に至った事故や、医師の診断を受け投薬や処理など何らかの治療が必要となった事故は原則として全て報告の対象となっている。
しかし同分科会で厚生労働省は、施設から上がってきた情報を市区町村で活用しきれていないとする調査結果を示した。事故情報の集計・分析の有無について市区町村に複数回答で聞いたところ、「件数を単純集計している」とする回答が59.3%と最も多く、「集計や分析は行っていない」も27.8%に上った。
施設側からは、市区町村への報告に当たり事務負担の重さを感じていることや、報告を行っても市区町村からのフィードバックを得られないことなどを課題に感じているとの回答が多くあった。
また厚労省からは、事故が起きた際に事業者は市区町村に報告を行うことになっているが、都道府県や国(厚労省)への報告は任意となっているため、一元的な情報の集約が行われていないことも示された。
議論では、国が情報を発信する仕組みを作ることや、報告の対象を見直すことなどを求める意見が出た。
田母神裕美委員(日本看護協会常任理事)は「介護現場には専門的な視点での分析やフィードバックが必要。県内や自治体内で発生した事故以外についても、国から情報が発信される仕組みを構築してほしい」と要望した。同様の声は小林司委員(連合・総合政策推進局生活福祉局長)からも上がった。事故情報の活用・フィードバックが進むよう、介護現場や市区町村への支援について、国からの後押しを求めた。
介護現場や市区町村の双方の事務負担の軽減策について、東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)が、報告対象の変更を提案。「死亡に至った事故はもちろん今まで通り報告対象とすべきだが、医師の診断を受け何らかの治療が必要となった事故については、軽微な擦り傷で消毒のみの治療であっても対象となってしまう。医師の診断を受け、医師が重大事故と判断したものに変更すべき」だと訴えた。
資料はこちら
ダウンロード
【資料5】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント
関連資料
[介護] 介護施設の3割、安全対策体制加算を算定せず 厚労省

