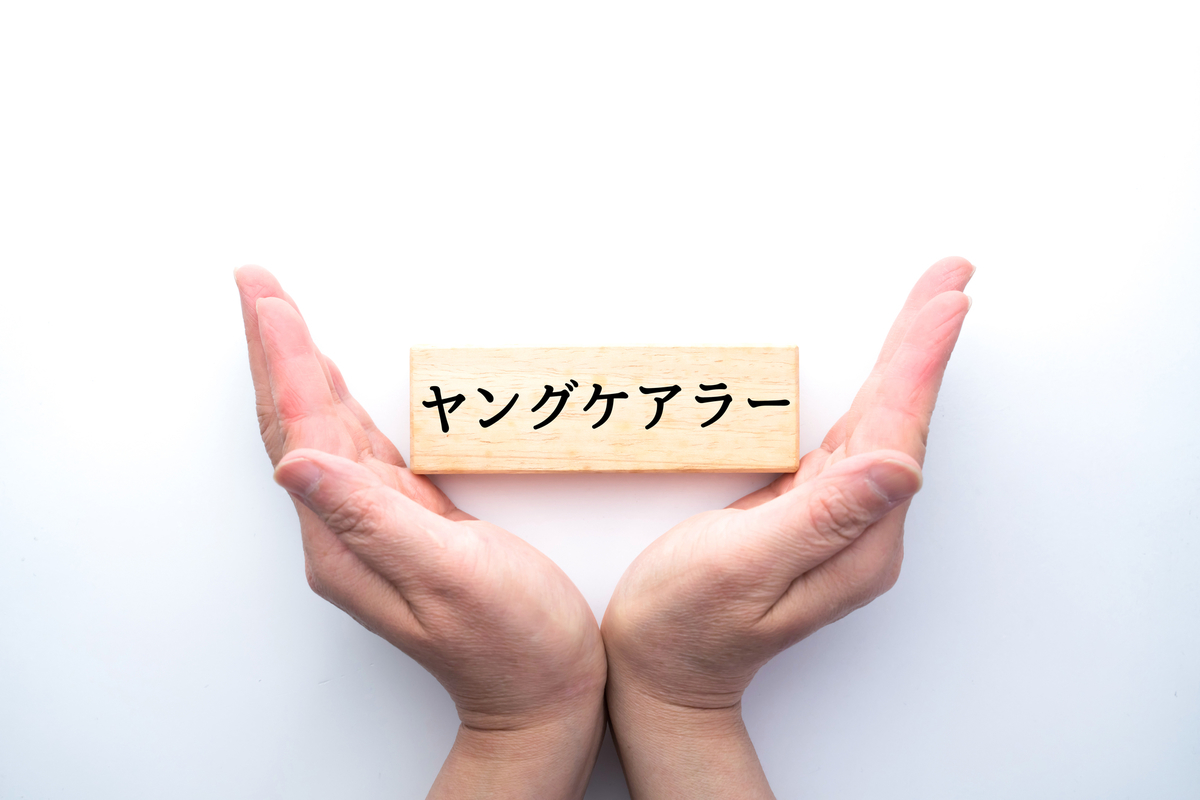
ヤングケアラーについて、国は2022年度から3年間を「集中取組み期間」と位置づけています。4月22日には、厚労省が「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」の周知を求める通知を発出しました。ケアマネおよび現場の支援職が、マニュアルを活かすために必要なことは何でしょうか。
事例のトップは「発見者がケアマネ」ケース
上記の支援マニュアルでは、ヤングケアラー支援事例(アンケート結果や有識者による助言をもとにした仮想事例)が紹介されています。そのトップで示されたのが、「ケアマネの発見から支援につながったケース」です。
事例内容は以下のとおりです。ケアマネが76歳の寝たきり状態の男性を担当しているというケース。その利用者の家族については、66歳の妻は認知症の症状があり、36歳の娘には精神疾患があります(夫とは離婚)。さらに、利用者には12歳の小学生の孫がいます。
その孫が祖父母や母親の世話(食事の用意と介助、洗濯、着替えの手伝いなどで1日おおよそ3時間)をしています。ケアマネには、「友達と遊んだり勉強する時間がとれない」と打ち明けた──という状況です。
当初のアセスメント時から、ケアマネは利用者の家族の状況を懸念し包括の担当者に相談しました。担当者は、上記のような孫の話をケアマネから聞き、学校関係者やスクールソーシャルワーカー、(母親の精神疾患に関して)行政の障害福祉担当者を含めたケース会議を開催。孫および母親に対しての課題共有と支援計画の検討を行なったというものです。
「家のことを知られたくない」の家族心理
ヤングケアラーをめぐる事例としては、典型的なケースと言えるかもしれません。ただ、同様のケースで常にケアマネが「ヤングケアラーの存在」に気づけるかといえば、状況次第となる可能性もありそうです。
たとえば、同事例の中で、ケアマネは精神疾患のある母親にも話を聞くシーンがあります。そこで母親は、「自分が精神疾患を有することはあまり人に知られたくなく、これ以上のかかわり(自分を含め、利用者以外の家族への支援)を求めない」としています。
ニーズがある人への意思確認をしっかり行なうことは、あらゆる支援業務の基本なので、こうした訴えが出てくることも想定されるでしょう。問題は、この意思が強い場合、アセスメント時に「家の中のことを知られないようにする」という行動が生じることです。
精神疾患の状態にもよりますが、ケアマネに対し「その場では自分の病気を隠そうとする」かもしれません。また、ケアマネの訪問時間について、利用者の孫が学校に行っている間を要望し、「ケアマネに本人を会わせない」ことを望む場合も可能性もあります。
状況が「隠される」場合のケアマネの対応は?
上記のような「行動」が想定される場合、ケアマネとしては限られた状況下で、ヤングケアラーの存在を察知しなければなりません。
もちろん、ケアマネはインテークやアセスメントに際して、ジェノグラム(家族関係図)を作成します。その時点で、「アセスメントに同席していない家族」の状況を推察するはずです。先の例でいえば、仮に母親が自分の病気を隠し、利用者の孫が同席していないとします。それでも、母親から聞く「普段の家族介護の状況」を聞いた際、さまざまな疑問や仮説が浮かんでくるはずです。
たとえば、「夫と離婚し一人親家庭なら、家計収入はどうなっているのか。母親は働いているのだろうか。何か理由(疾患など)があって働けないのだろうか。いずれの場合でも、親の介護(しかも利用者の妻の方は認知症がある)を1人で担えるだろうか。利用者の孫の役割も大きいのでは…」という具合です。
ケアマネとしては、まず「家族介護者の負担」という観点から(ヤングケアラーの母親に)「お仕事をされているかどうか」を尋ねるでしょう。これは、「これまで家族によってなされてきた介護の状況を知る(生活援助を調整する場合の判断基準にもなる)」という正当な理由があります。ただし、「聞いてもいいか」という当事者への了承を求めることは必要なので、相手が嫌がれば検証できません。
支援へのタイムラグを埋めるのに必要なのは
結局は、相手との信頼関係を築く中で、初めて検証可能な情報が得られる─となるかもしれません。問題は、そのタイムラグです。事例では、ヤングケアラー本人やその母親から話を聞けたという前提のもと、ケアマネが「(ヤングケアラーに)今すぐ命に危険がおよぶ状況ではない」と判断したうえで包括に状況を報告しています。では、情報収集に時間がかかる場合はどうすればいいのでしょうか。
情報収集が困難というのは、恐らくヤングケアラーが通う学校でも同じでしょう。母親が定期的な精神科通院を行なっていない場合、医療機関でも状況がつかみにくいことがあります。既存の職種だけでは、先の「タイムラグ」はどうしても生じやすくなるわけです。
となれば、わずかな初期情報を早期に集約し、専門的な見地から判断していく新たな専門職が求められます。厚労省は2022年度予算で「ヤングケアラー・コーディネーター」の設置を進めようとしていますが、確かな情報が上がってから支援機関につなぐだけでなく、初期時点からの確かな判断機能・権限を持たせることが必要でしょう。厚労省および自治体としては、ケアマネなど既存の支援専門職から多様なケースをヒアリングしつつ、現場実態に沿った対応策が求められます。

◆著者プロフィール 田中 元(たなか はじめ)
昭和37 年群馬県出身。介護福祉ジャーナリスト。
立教大学法学部卒業後、出版社勤務。雑誌・書籍の編集業務を経てフリーに。高齢者の自立・ 介護等をテーマとした取材・執筆・編集活動をおこなっている。著書に『ここがポイント!ここが変わった! 改正介護保険早わかり【2024~26年度版】』(自由国民社)、 『介護事故完全防止マニュアル』 (ぱる出版)、『ホームヘルパーの資格の取り方2級』 (ぱる出版)、『熟年世代からの元気になる「食生活」の本』 (監修/成田和子、旭屋出版) など。おもに介護保険改正、介護報酬改定などの複雑な制度をわかりやすく噛み砕いた解説記事を提供中。

