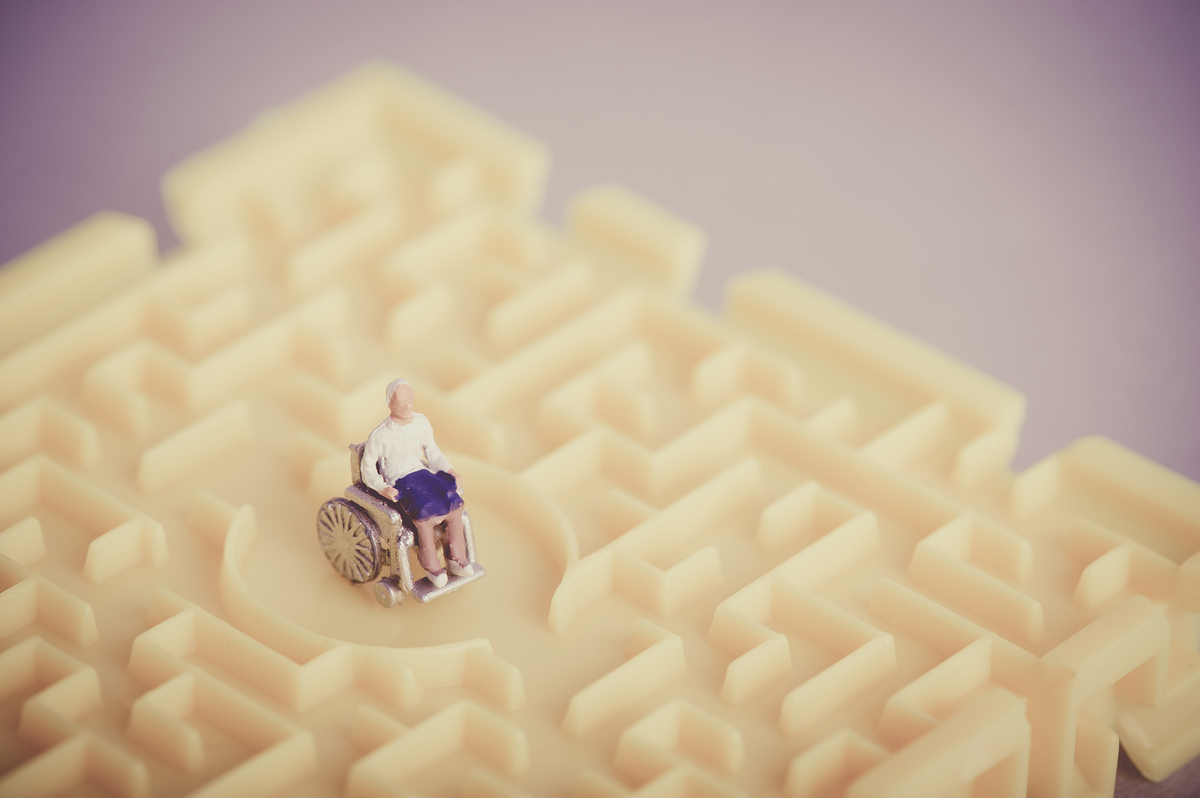
介護保険制度の見直しに向けて、利用者負担増や給付制限の多くが見送られるかもしれない…という見方が強まっています。一方、財務省の財政制度等審議会は実施を強く求める姿勢を崩していません。その1つが、要介護1・2一部サービスの総合事業への移行です。
一見、強硬姿勢は収まったように見えるが…
財政制度等審議会が示した「令和5(2023)年度予算の編成等に関する建議」では、要介護1・2の訪問・通所介護の地域支援事業(総合事業)への移行に関し、生活援助サービスを始めとして「段階的」な移行を提言しています。これだけを見ると、身体介護や通所介護を含めた移行について、次期改定を目指すような強い提案は影を潜めたかに思われます。
しかし、注意したいのは建議内で述べている提言の根拠です。ここに、総合事業への移行を懸念する立場の見解との大きな隔たりが見られます。この「隔たり」がある限り、懸念材料の払拭に向けた政府全体の認識が深まらないままの施策遂行となりかねません。
その結果、「段階的」であっても、その間の国による適切なフォローが抜け落ちたまま、将来的に訪問・通所介護全体の移行につながる恐れが大きいと言えます。介護保険制度の(それがあってこそ被保険者による保険料負担の納得につながる)信頼性の確保を図るうえでも、財務省側の根拠の不十分さをきちんと指摘していく必要があるでしょう。
財務省側の建議の主張内容を掘り下げると…
建議を見ると、「地域支援事業(総合事業)への移行に対しては、介護サービスの質や量の低下を懸念する向きがある」と、反対意見が強い今の状況に言及しています。そのうえで、懸念の声に対する反論を述べています。
1つは、「地域支援事業の利点は、地域の実情に合わせ、訪問介護・通所介護をニーズに応じて工夫できる点」にあるとしたうえで、その利点を活かせば、「各保険者が要介護者の満足度を高めるように介護サービスを独自に企画・実施」できるという理屈です。
ここで言う「地域の実情」とは、その前の文脈から「介護ニーズの増加の一方で、従事者不足が深刻化する」といった状況を指していると思われます。その対応策として「人員配置や運営基準の緩和等」を通じた「多様な人材や資源の活用」を上げ、その部分における保険者の「独自の企画・実施」が「要介護者の満足度を高める」としています。
もう1つは、「多様なサービスを活用することで、各利用者の状態を踏まえながら、介護職員がより専門性の高いサービスに注力することが可能になる」というもの。より重度の人に給付サービスを集中させることで、制度の効率化を図る道筋を示したわけです。
サービス環境の厳しさへの解決提言ではない
要するに、ニーズの高まりと資源の不足という危機においては、基準緩和等の保険者努力が不可欠であり、それがないと現行のサービス水準の維持が困難になるという前提があるわけです。「要介護者の満足度の向上」は、あくまで「水準維持が困難になるよりは“まし”」という理屈の上に成り立っていると考えていいでしょう。そのうえで、「より重度になったとしても、(基準緩和等による)サービスの集中提供で乗り越えることができる」というメリットを主張していることになります。
お気づきのように、上記の理屈は「サービス環境の厳しさ」を根本から解決するビジョンの上に描かれているわけではありません。また、要介護1・2の場合、“まし”では済まない事情──認知症によって生活困難になりうる状況が相当程度あること──があり、懸念する側の多くはその点を問題にしています。それに対する回答になっていないわけです。
認知症日常生活自立度から見える「実態」
介護保険部会で提示された資料では、要支援・要介護認定の一次判定時における「認知症日常生活自立度Ⅱ以上」の人の割合データが示されています。それによれば、要支援1・2が9%前後であるのに対し、要介護1・2になると70%前後に跳ね上がります。
加えて、東京都が2020年に公表した調査では、「認知症日常生活自立度Ⅲ以上」の人の割合は、要介護1で約18%、要介護2で約25%に達しています。Ⅲといえば、ⅢaでBPSDの悪化による異食や蒐集、徘徊、失禁、不潔行為および火の不始末が見られ、明確に「介護を要する」と定義づけられています。
Ⅱの「誰かが注意していれば自立できる」というレベルとは状態は明らかに異なり、まさに今回の建議で言う「介護職員による専門性の高いサービスの注力」が必要になるレベルです。そうした人が要介護1・2で2割程度いるわけですから、財務省側の主張と現実の間に大きな隔たりがあることがわかります(ちなみに、要支援1・2ではⅢ以上の割合は約2%と、要介護1・2の10分の1)。
仮に要介護1・2の一部サービスを総合事業に移行するのなら、どこかで認知症対応を強化するしくみが必要です。現状の地域支援事業(認知症総合支援事業)でそれが可能かといえば、専門職を投入する分、事業費の大幅な上乗せが必要です。試算にもよりますが、介護給付によるサービスのまま制度改善を図る方が効率的という見方も出てくるでしょう。
財務省の使命は、各制度がその目的を達成するうえで最良の方策を導き出すことにあるはずです。実態から大きく外れた前提で制度の根幹を揺るがすことは、かえって貴重な財源を浪費することにつながりかねません。
![]() 【関連リンク】
【関連リンク】
財政審、要介護1と2の保険外しの断行を要求 「ためらうべきではない」|ケアマネタイムスbyケアマネドットコム
参考資料:令和元年度認知症高齢者数等の分布調査報告書(東京都福祉保健局高齢社会対策部計画課)※認知症日常生活自立度の割合は30ページ

◆著者プロフィール 田中 元(たなか はじめ)
昭和37 年群馬県出身。介護福祉ジャーナリスト。
立教大学法学部卒業後、出版社勤務。雑誌・書籍の編集業務を経てフリーに。高齢者の自立・ 介護等をテーマとした取材・執筆・編集活動をおこなっている。著書に『ここがポイント!ここが変わった! 改正介護保険早わかり【2024~26年度版】』(自由国民社)、 『介護事故完全防止マニュアル』 (ぱる出版)、『ホームヘルパーの資格の取り方2級』 (ぱる出版)、『熟年世代からの元気になる「食生活」の本』 (監修/成田和子、旭屋出版) など。おもに介護保険改正、介護報酬改定などの複雑な制度をわかりやすく噛み砕いた解説記事を提供中。

