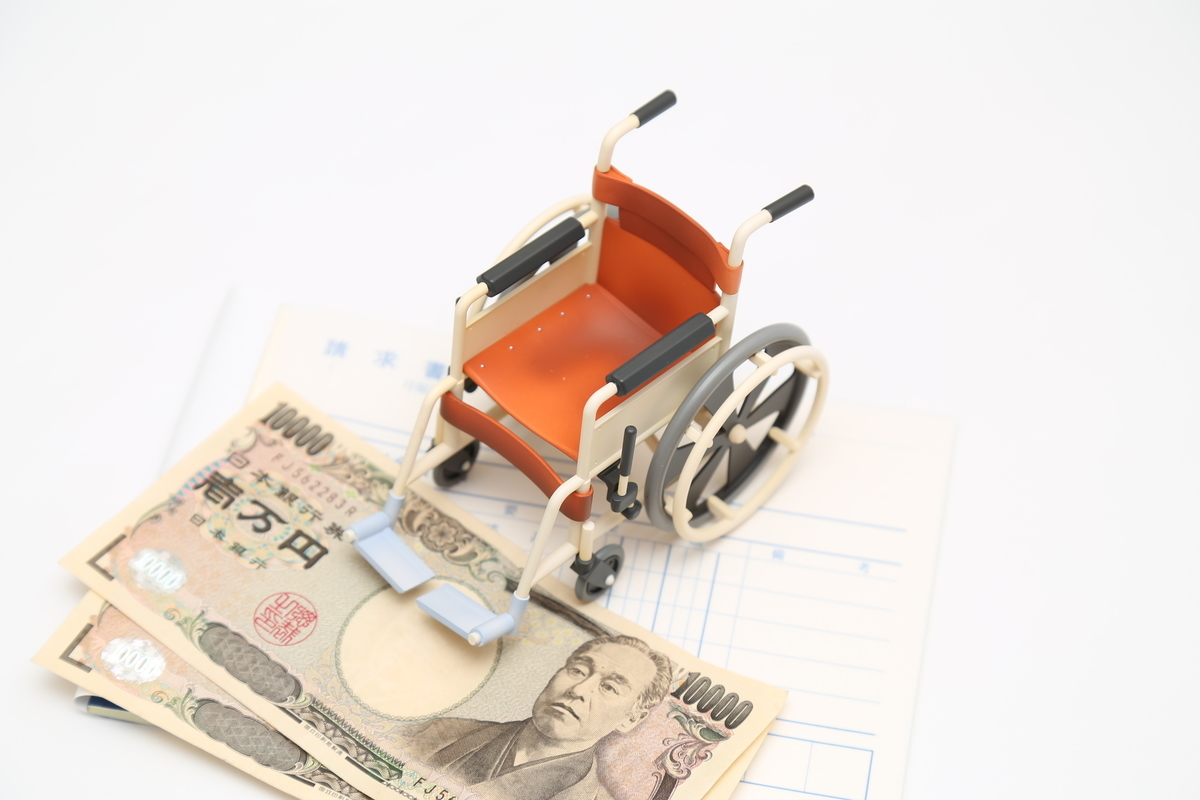
社会保障制度の改革に向け、経済界からの要望や提言が活発化しています。経済3団体のうち、経済同友会からは「持続可能な財政構造の実現に向けて」と題した政策提言が出されました。その中で、医療・介護給付を抑制するための「サーキットブレーカー」の導入という刺激の強い提案も見られます。
経済成長率にもとづいて給付を決定する!?
「サーキットブレーカー」とは、本来は電器用語で「電流の流れ過ぎを防ぐための遮断器」を意味します。経済面では、株式相場で相場の急変動が生じた場合に発動する「取引中断システム」を指す用語としても用いられます。
この考え方を、医療や介護の給付に適用するというのが、今回の提言です。簡単に言えば、「企業や社員の保険料負担」(電流)が一定程度上昇した場合に、「給付の伸びが経済成長率を上回らない」ようにするしくみ(遮断器)を導入するというものです。
現行では、たとえば介護給付費の基準を決めるのは厚労大臣であり、その決定に際しては社会保障審議会(介護給付費分科会など)の意見を聴かなければならないとされています(介護保険法第41条第5項より)。
その時々の報酬改定率は、実質的に政府内の大臣折衝等で決定されます。とはいえ、少なくとも審議会(各事業者団体・職能団体等のヒアリング含む)の意見(答申)を受けることは、法律で定められている手続きです。自動的に介護給付の水準を決めるしくみが発動されるとなれば、上記の手続きが意味をなさなくなる恐れも生じます。
当然、介護保険法の改正が必要になるが…
もっとも、今の状態で「サーキットブレーカー」を導入しても、「それに従う」ための法的根拠はありません。当然、介護保険法(第41条第5項)の改正をもって、審議会の議論との関係を明確することが必要です。今提言が目指すのも、そうした法改正です。
では、医療や介護に向けられるニーズと(提言にある)経済成長率を連動させることで、どのような影響がおよぶでしょうか。たとえば、「経済が成長しなければ給付は増えない」という点がルール化されれば、現場のニーズがどんなに高まっても、低成長の間は介護報酬のアップは期待できない──となります。
サービスの運営環境が悪化しても、介護報酬は増えない──そうした制約がある業界で「将来に期待して働こう」と考える人がどれだけいるでしょうか。結果、人手不足を加速させるとなれば、人手不足からの事業所の閉鎖・撤退なども劇的に増える恐れもあります。
そうなると、親の介護等で安心して働けない、あるいはヤングケアラーのように将来進むべき道を定められないという状況も高まりかねません。皮肉にも、「経済成長」が停滞するという逆循環も生じることになります。
昨年の政策提言でも同様の主張が見られる
そのような「劇薬」を、経済団体として本当に導入すべきと考えているのでしょうか。実は、この「サーキットブレーカー」については、今回の政策提言が初見ではありません。2021年7月の「活力ある健康長寿社会を支える社会保障のあり方」という政策提言でも取り上げられています。
この時の提言では「医療・介護給付の伸びと経済成長との乖離を抑制」することが、「社会保障制度の持続可能性を高める方策」であると明確に位置づけています。そのうえで、医療・介護保険制度にも、年金制度と同様に「収入が支出を決めるしくみを導入すること」を求めています。その具体策が「サーキットブレーカー」となるわけです。
もちろん、介護業界および職能の団体からは強い反発が予想されます。医療給付も対象としている点では、医師会等の医療系団体からの異論も厳しさを増しそうです。社会保障そのものの位置づけにもかかわるテーマであるだけに、現実化するとなれば、非常に高いハードルが待ち受けることになるでしょう。
経済団体が「実現」を目指している改革とは?
もっとも財政をつかさどる財務省としては、今後前向きになる可能性(2023年度予算に向けた提言に反映させるなど)もあります。たとえば、この「サーキットブレーカー」を「他に財務省が打ち出している改革」との交換条件的な扱いとしてくるかもしれません。
すでに財務省が強く打ち出している改革案といえば、「2割負担の拡大」や「ケアマネジメントへの利用者負担導入」、「要介護1・2の訪問・通所介護の地域支援事業への移行」の3つです。これらについて、「実現できないのであれば、サーキットブレーカーのしくみを導入せざるを得ない」という理屈に持ち込むことが考えられるわけです。
ちなみに、3大経済団体のうちの経済団体連合会は、かねてから財務省の3つの改革案とほぼ同じ提言を出しています。つまり、経済界としても実現を強く求めているのは先の3つであり、経済同友会の「サーキットブレーカー」はそれらの実現を誘導するうえでの交渉材料と位置づけてくるかもしれません。
もっとも、経済団体の認識を見ると、介護現場とのズレは見た目以上に深いといえます。たとえば、経済同友会が2020年10月に出した提言では、介護現場の人手不足の要因として「介護福祉士よりもケアマネの方が報酬が高いこと」をあげています。ケアマネの給与額を人手不足の要因としている点で、現場としては眉をしかめる人も多いでしょう。
こうした経済団体の意向が、どこまで地に足のついた改革議論となりえるのか。現場としても、頭に入れておくことが必要です。

◆著者プロフィール 田中 元(たなか はじめ)
昭和37 年群馬県出身。介護福祉ジャーナリスト。
立教大学法学部卒業後、出版社勤務。雑誌・書籍の編集業務を経てフリーに。高齢者の自立・ 介護等をテーマとした取材・執筆・編集活動をおこなっている。著書に『ここがポイント!ここが変わった! 改正介護保険早わかり【2024~26年度版】』(自由国民社)、 『介護事故完全防止マニュアル』 (ぱる出版)、『ホームヘルパーの資格の取り方2級』 (ぱる出版)、『熟年世代からの元気になる「食生活」の本』 (監修/成田和子、旭屋出版) など。おもに介護保険改正、介護報酬改定などの複雑な制度をわかりやすく噛み砕いた解説記事を提供中。

